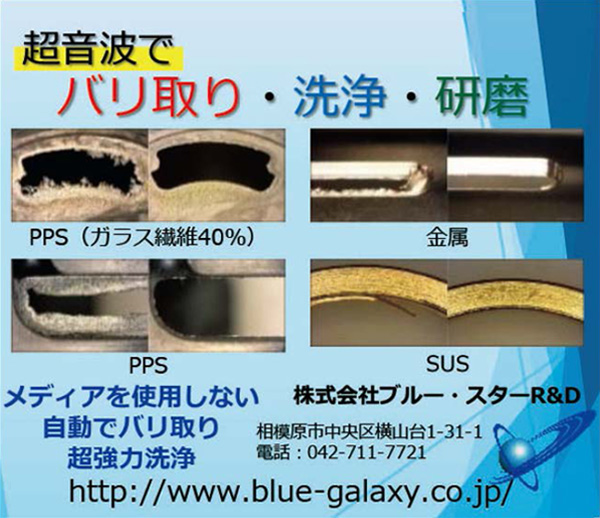シラド化学(横浜市金沢区福浦)は、「ガソリン着色剤」で国内シェア7割を占めるオンリーワン企業だ。もともとは無色透明に近いガソリンを、灯油などとの混同を防ぐ目的で色付けする着色剤を製造販売し、石油元売り企業などに出荷するメーカー。脱炭素化の流れが進む中で事業再構築を模索し、ガソリンから工業用市場に視野を広げ、「潤滑油の添加剤」の輸入販売事業に進出した。その際、販路を新規開拓するのではなく、既存顧客への新たな商材として提案。販売数量を増やし、今では売上高の6割を占めるまでになり、会社全体の売り上げも10年前の2倍に拡大させた。成熟産業にあったとしても「変わる」ことで成長を遂げた実例だ。
ガソリン着色料から潤滑油添加剤へ
1951(昭和26)年の創業。2021年4月に就任した白土和弘社長は4代目。創業以来「色のメーカー」としてガソリンやオートマオイル(ATF)、エンジンオイルといった潤滑油の着色剤の製造販売を手掛ける。
着色剤はガゾリン1リットルに対して数ppm入れることで“ガソリン色”になる。現在、年間400トンほどを生産する。
白土社長によると、国内で着色剤を扱う企業は5社ほど。その中でも同社がトップシェアという。「(着色剤市場は)ガソリンが生活必需品であるため、景気の波の影響を受けにくいです」(白土社長)。
だが、脱炭素化の流れは業界にも大きな影響を与える。着色剤の最終ユーザーとなる自動車産業も、電動車両へのシフトが進む。無論、同社も変革を迫られることになった。
白土社長は専務時代から新事業を模索。そして「自動車やガソリンではなく、“工業用”だったらどうなのか。『油』の需要は無限にあるはず」と視点を切り替え、工作機械や船舶、農業機械などで使用する工業用潤滑油向けの添加剤の販売を始めた。
潤滑油の添加剤は、機能性をアップさせる目的で使用する。ただ、同社は大きな設備投資を必要とする製造をするのではなく、優れた商品を持つ海外企業から輸入販売する“商社”に特化した。
とはいえ「これまでのようなメーカー事業と商社では、ビジネスモデルがまったく異なっていました」(白土社長)と、貿易の知識などをゼロから身に付ける必要があったという。
そうした努力が奏功し、イタリアの潤滑油添加剤メーカーの日本総代理店になり、最近ではインドメーカーとも代理店契約を結んだ。
白土社長は明かす。「自社で新商品を開発し、新市場を開拓するのが一番難しいです。かといって、既存商品を新しい市場に持っていくのも難しいです。だったら、既存顧客に対し新しい商品を提案する方が効率的です」
輸入した添加剤は、着色剤の販売先である元売り各社や潤滑油メーカーに売り込んだ。商社事業は年々拡大しており、遂に創業以来の本業である着色剤の売上高を超えた。「商社部門を立ち上げていなければ会社の売り上げは減少していました」
また、新たな柱へと育成しているのが、敷地内のスペースを活用した「小分け受託事業」だ。危険物や化学製品を扱っているノウハウを生かし、大きなタンクで運ばれてくる輸入業務用洗剤を容器に小分けする作業などを請け負っている。
「輸入もして、モノも作れて、小分けもできて、自社商品やOEMも手掛けられる“ケミカルのマルチプレーヤー”を目指しています」と白土社長。
同社の挑戦は、家族や親族らが営む会社の若手後継者が、先代からのインフラを生かしながら新事業などに挑む「ベンチャー型事業承継」の一例といえる。